|
| |
|

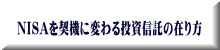
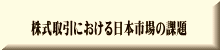
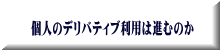
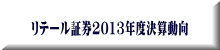
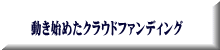
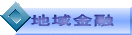

|
| �R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�ɂ��� |
|
|
|
|
|
|
�@��Ђ͒N�̂��̂��A�Ƃ������R�[�|���[�g�E�K�o�i���X��̋c�_�����鎞�A����͉�ЂƂ����g�D���ɂ����Č��͂�L����o�c�w������������A�Z���I���v�̒Nj�����A�g�D�ɂƂ��Ď��ɉ��\�Ǝv����v�������銔��̍s�ׂ𐧌����悤�Ƃ����Ӑ}���܂܂��ꍇ�������B
�@�ܘ_�A��Ђ͊�����܂ރX�e�[�N�z���_�[�̂��́i�Љ�S�̂́j�ł��낤���A���J��Ђ̏ꍇ�́A�s��̋@�\���g���Ď������B������̂�����A�����ƂƂ���������������̃X�e�[�N�z���_�[�Ɋ܂߂�K�v������B
����}�̐V�����ɂȂ��ĐV���������ڂ���邪�A�}�j�t�F�X�g�ɂ͂Ȃ��������̂̐���h�m�c�d�w�Q�O�O�X�ɂ͌��J��ЂɓK�p�������ʖ@�Ƃ��Č��J��Ж@�̌���������B�ړI�́A���J��Ђ̏��J�����v�č��Ȃǂ��������A���S�ȃK�o�i���X�i��Ɠ����j��S�ۂ���ׂł���B����}�ɂ́A���J��Ж@�v���W�F�N�g�`�[��������A�V���ɓZ�߂�ꂽ�f�Ă��X���P�S���̓��o�ł͓��W�L���ƂȂ��Ă���B
�@���̑f�ẮA���{����������o�ύ��������c�̃��[�L���O�O���[�v�Ō�������Q�N�O�ɓZ�߂�ꂽ�g���J��Ж@�v�j�āi��P�P�Łj�h���x�[�X�ɂȂ��Ă���悤�����A���X�̗v�j�Ăɂ́A�]�ƈ���\���č�����ɎQ������Ă͂Ȃ������B
�����ŁA�ړI�Ƃ��Ă���R�[�|���[�g�K�o�����X�����̈�A�̓����ɂ��Đ������Ă��������B
���̂����A�G��������[���h�R���̕s���Ɍ��炸�A���{�ł��A���U�L�ڂ�U�����Ȃǖ��炩�Ȃ�s�@�s�ȊO�ɂ��A��ʂ̑�O�Ҋ���������啝�Ȋ��������E�����ȂǏ�������Ƀ_���[�W��^���鎑�{����Ȃǂ��������B�o�c�҂̍s���߂����s�ׂ�N���`���b�N����̂��A�o�c�҂��m��Ȃ������Ƃ�����Ђ̘c�݂��ǂ��C������̂��B
���̃R�[�|���[�g�K�o�����X�����Ɋւ��ẮA�Q�̗��ꂪ���������A��͊J���̓O��A������͌o�c��Ɩ��Ɋւ���Ď��@�\�̋����ł���B
�y�J���̓O��z
��Ж@��ł́A���������V�X�e���\�z�̊�{���j�̖������`���t���i���Ёj�Ƃ��̎��ƕł̊J���B
���Z���i����@�ł́A�l�����J���E�����������̒�o�B
������J���ł́A�K���J���i�^�C�����[�f�B�X�N���[�W���[�j�̍X�Ȃ�O��A�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X���̏[���B
�����̌��ʂƂ��āA���J��Ƃ̊J�����S�́A�������N�����ɏd���Ȃ��Ă��Ă���B
�y�Ď��@�\�̋����z
�E�i�|�r�n�w�@�Ή��Ƃ������ƂŁA���������V�X�e���̍\�z�����J��Ƃ͂������N���߂��Ă����B
�E�l���`��l�a�n�ȂǂŁA�o�c�҂Ɗ���̗��v���������O�����悤�ȏꍇ�A�ŋ߂͑�O�҈ψ����ݒu���āA�O���ӌ��������\����P�[�X�������Ă���B
�E�ЊO������̓Ɨ����Ɋւ��ẮA�@�֓����Ƃ�C�O�����ƂȂǂ���Ɨ������������߂铮���������A������ď��K�������̓���������B
�E�č����̊č��@�\�����ɂ��ẮA���Ђ͔����ȏ�̎ЊO�č������K�v�ŁA���̊č��@�\�����ׂ̈ɂ��A�č���I�C�ւ̊č�����Q����č��X�^�b�t�̏[�������邽�߂̏��K�������̓���������B
�܂�A�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̋����Ɋւ���J���Ή��́A���ݑ����s���Ă��邵�A�Ď��@�\�̋����ɂ��ẮA������̏��K���őΉ����悤�Ƃ��铮��������B
�@��Ж@�E���Z���i����@�E���K���Ɗm���ɂR�ɂ킩��Ă��鎖���A���J��Ж@�Ƃ��Ĉ�Ɏ��܂Ƃ߂邱�Ƃ͈ꌩ�����I�ɂ��v���邪�A���ƃR�[�|���[�g�E�K�o�i���X������ڎw���̂ł���A���͍ŋߎ��g�܂ꂽ���X�̎{��̎����������ɂ߂鎖�ƁA���̂U���܂ŋc�_����Ă����K�o�i���X������𑁋}�Ɏ�����K���Ɏ�荞�ݎ��������グ�鎞���ł͂Ȃ����낤���B
�@���J��Ђ́A�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�����͖ܘ_�K�v�����A��ƂƂ��Đ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�܂��A���̃e�[�}�Ƃ��Ăh�e�q�r�i���ۍ�����j�ւ̑Ή����T���Ă���B
���J��Ƃ̂�����ɂ��āA��ɋc�_���Ă������Ƃ͕K�v���낤���A�����c�_�ɂ�鍬���́A�X�e�[�N�z���_�[�������ė~�����Ǝv�����Ƃł�����B
|
��Ђ͒N�̂��̂��Ƃ������ɁA��Ђ͊���̂��̂ł����邪�A�����œ����l��A�����ȂǃX�e�[�N�z���_�[�̂��̂ł�����B�������N�A�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X����Ɍ�������g�݂́A�o�ώY�ƏȂ̌�����E���Z���̋��Z�R�c��E�����ē��Ȃǂŋc�_����Ă������A�ǂ��炩�Ƃ����Ɗ���Ⴕ���͏�������ł��铊���Ɗ��ł�������������Ȃ��B��Ƒ��̗���ł́A���̂S���ɁA�o�c�A���A�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�ɂ��Ă̎�v�_�_�̒��Ԑ����Ƃ��Ē��s���Ă���̂ŁA���̊T�v���Љ�Ă����B
�\�č�����ݒu��Ёi���؏���Ƃ̖�X�V���j�ɂ�����K�o�i���X�����ɂ���
�y�_�_�P�F�ЊO������̐ݒu�`���ɂ��āz
���؏���Ђɂ����Ă��A�����ȏ�͎ЊO�������ݒu���Ă��Ȃ��B�������A��������⊮����ړI�ŎЊO�L���҂ɂ��A�h�o�C�U���[�E�{�[�h��ݒu���Ă����Ƃ�����B�č��̗l�Ɏ�����K���ŎЊO�����ݒu���`���t���Ă��A�s�ˎ����N����ꍇ���ڂɂ��̂ŁA�`���_�ł̋c�_�͖��Ӗ��B�e��Ƃ̎���I�I�����F�߂���ׂ��B�܂��A��Ƃ͓����ƂƂ̉�b�𑝂₷�w�͂��h�q�����Ȃǂŋ������Ă��āA��������K���Ȋē��s��������\�͂����邩�A����͓��[�s���Ŕ��f�ł���B�����Ƃ���ЊO����������߂鐺������Ȃ�A�e��Ƃ��h�q������ʂ��Ē��J�ɐ������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƁB
�y�_�_�Q�F�ЊO���v���̓Ɨ����v���ւ̌������ɂ��āz
�@�@�֓����Ƃ�C�O����A�e��Ђ����擙�̎ЊO������ɑ���ᔻ������B�o�c�w����̓Ɨ����Ɋւ��Ă͋c�_����Ȃ���Ȃ�Ȃ����A�t�ɃX�e�[�N�z���_�[�̈���Ƃ��ĊO���̗���Ŋ�Ɖ��l�̌���ɖ𗧂��Ă���ʂ�����B���̎ЊO���ɂ��ẮA������J���Ȃǂŏ[�����Ă��Ă���̂ŁA���l����F�߁A�ŏI�I�ɂ́A�I�C���銔�傪���f���錻�s�̎d�g�݂��]�܂����B
�y�_�_�R�F�č����̖����ƌ����̋����ɂ��āz�i�ЊO�����ݒu��ЊO���̓Ɨ��������Ȃǂ������A�č����̌������������Ă͂Ƃ̍l�������邱�Ƃɂ��āj
�@���݂̉�Ж@��A���ɁA�č����ɂ͎�����ƂƂ��ɋƖ����s�ɑ���č��������^�����Ă���B���̌������\���@�\������ׁA�e��Ƃ͊č����Ɩ����T�|�[�g���鎖���Ǒ̐��̏[���������������Ƃ̘A�g�����ȂNJe��Ƃ��w�͂��Ă����ׂ��B
�y�_�_�S�F��v�č��l��I�C������A��V�����肷�錠�����A���������č����Ɉڂ��ׂ��Ƃ̋c�_�ɂ��āz
�@��v�č��l�I�C�E��V����Ɋւ��ẮA���Ɋč����ɂ͉e�����s�g���錠��������B�č����ɁA��v�č��l�̑I�C�c�Ă��V�����肷��Ƃ����Ɩ����s������^���邱�ƂɂȂ�A�č����͌o�c�w����̓Ɨ��̑��݂Ƃ��Ă̊ē@�\���ʂ����Ƃ������x��|�ɔ����A�Ɩ����s�ƈӎv����̓��������炵���˂Ȃ��B�i�M�Ғ��F���̕����͕������̂ŁA��v�_�_�̒��Ԑ����i�T�v�j�̋L�ڂ��̂܂܁j
�y�_�_�T�F����ɂ�����c�����s�g���ʂ̌��\�z
�@�ŋ߂͑������������Ƃ͂����A����ł�����c�Ă̓��[���ʌ��\�͂R�O�Ў���x�B����Ƃ̃R�~���j�P�[�V��������w�[��������ϓ_����]���ł��邪�A�����I�Ɋ��呍����o�Ȃ̎^�ۂ̏ڍW�v���ȗ����Ă���ꍇ������B�܂����[���ʂ��L�����\���邱�ƂŁA���呍��̊O����̉e���͂����傷��S�z������A�X�̊�Ƃ̔��f�Ɉς˂�ׂ��B
�y�_�_�U�F��K�͑�O�Ҋ����ɂ��āz
�@�L�����s�łȂ�����A���������͈̔͂Ŏ������Ɏ������ꂽ�����ł͂��邪�A���傪�\�z���Ȃ��x�z���̈ړ���A�����̊��͖��B���s��ЂƂ��ẴA�J�E���^�r���e�B���[�������A��������̌������s���ɚʑ�����Ȃ��悤�A������ł̊�����ɑ�������R����J���͏[�������ׂ��B
�@����Ƃ̊J�����S�́A�l�����J���E�����������ȂǑ����ɏd���Ȃ��Ă��邵�A�h�q�R�X�g���������Ă���i���{�h�q���c��ׂł́A�Q�O�O�W�N�̂h�q�R�X�g�͂P�Г�����Q,�Q�P�O���~�Ƒ啝�ɑ������Ă���j�B�܂��A��L�̂悤�Ȃ��Ƃ��A�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�����ړI�ŁA�S�ď��K�������Ă��܂��̂��A�r���Ń��[����ύX���鋣�Z�̂悤�ŁA���Z�Q���҂Ƃ��Ă̊�Ƃ͕��S�Ɋ�����̂��낤���B
�@�������A��ƂƂ��ăR�X�g���]��|����Ȃ��o�c���f�ɂ�邱�ƂȂ�A�����ƁE����Ƃ̉�b���i���^�c�̓������m�ۓw�͂ȂǁA�����I�ȕ������őΉ����Ă������������B
|
|
�،��Ƃ����Z�T�[�r�X�ƂȂ̂�����A�T�[�r�X���鑤�̓����Ƃ��A����]�艽��s���Ɏv���Ă���̂��A�l�̏ꍇ�ɂ��ď����l���Ă݂����B
�@���Z��������I�Ɍ��\���Ă���g�u���Z�T�[�r�X���p�ґ��k���v�ɂ����鑊�k���̎�t���h�̂S���`�U�����ł́A�l���瓯���k���ɖ����Q�O�O���ȏ�̋��Z�T�[�r�X�Ɋւ��鎿��E���k�E�ӌ��������Ă���悤�����A���̓���R�O���R,�W�P�T���͓������i�E�،��s�ꐧ�x���̋��Z���i����@�֘A�����،��֘A�Ɩ����ł���B
�@��v�ȏ،��Ɩ��ʂɁA���̑��k���̎�����e���݂Ă݂�ƁA
�y���Z���i�̔̔��Ɋւ��āz
�E�����A���A�����M�����̋��Z���i���w�����悤����ہA���Y�̏��ڂ��������ꂽ��A�����Ԃ̐������Ȃ��Ă͂����Ȃ����Ƃ̖₢�B
�����Z���i����@�ɂ��A�_������O�̏��ʌ�t�`������������A���Z���i�̔̔����ɁA�K�����̌����̊m�F���̍s�K��������ׁA���߂Ă̌ڋq�Ɋւ��Ă͒����Ԃ̐����E�m�F�s�ׂ��s�Ȃ��Ă���悤���B
�������A�ڋq���s���Ɋ����Ȃ����ԓ��ł̑Ή����o����悤�A�m�F��Ƃ̌�������l�b�g���p�Ȃǂ́A�T�[�r�X�ƂƂ��Ď��g�މۑ�Ȃ̂��낤�B
�y���M�̔̔��Ɋւ��āz
�E��s�œ����M�����w������ۂ̒��ӂɊւ���₢�B
����s�E�X�ǂł����M�̍w�����\�ƂȂ�̂͗ǂ����ŁA�����ł��̓��M��̔����悤�����Z���i����@��́A�O�q�̂悤�ȋ`���ƍs�K���ɑΉ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����A��s�Ŕ����Ă�����̂͌��{���ۏ����ƍ��o���铊���Ƃ�����̂ł���A���Z����̖��̂悤�ȋC�����邪�A�����ƂƂ��Ă̎��������߂���̂ł͂Ȃ����낤���B
�y�����J�����ɂ��āz�i����͖����J���֘A�̑��k���啝�ɑ����Ă���j
�E���Z�����Ƃ̊W���x���āA�����J�������U������A����������E�߂��肷��Ǝ҂Ɋւ��鑊�k
�E���ɍw�����Ă��関���J�����Ɋւ��āA���������┃���Ɋւ��鍼�\�I�s�ׂɊւ��鑊�k
�E�Ǝ҂���A�l�オ��m�����̊��U�����������k
�E�w�����������J���̖��`�������ɉ����Ȃ��Ǝ҂ɑ��鑊�k
�E���Ɖ�Ђ���̖����J�����U�ɂ��鑊�k
���h�o�n�s�ꂪ�ᒲ�Ȃ̂ɁA��ꓙ��O��ɂ��������J�����U�Ɋւ��鑊�k���������Ă���͔̂瑊�ȑz��������B���ɂ́A��荞�ߍ��\�I�Ȏ��������悤�����A���ʁA�������҂̂��関���J�������Ɋւ��āA�l�����Ƒ��̋������҂�����̂���B�������A�ƊE�Ƃ��Ă��̐�����Ɠ����j�[�Y�ɉ�����w�͂��s�����Ă���̂��A�����ł͂Ȃ����낤���B�h�o�n��Ƃ����Ȃ��̂́A�R�����[���̌��i���ɋƊE����肭�Ή����Ă��Ȃ����ʁi�����Čo�ς�s���������ł͂Ȃ��j�����A�����J���ŗB�ꊩ�U���F�߂��Ă���Ƃ����O���[���V�[�g�s������́A���ۂɎ�舵��Ȃ��،���Ђ������A������ʂ̓����Ƃ��牓���B
�x���`���[�����Ɋւ��ẮA���x���`���[�t�@���h�⏊���T�����P�O�O�O���~�߂��܂Ŋg�傳�ꂽ�G���W�F���Ő��Ȃǂ̎{���邪�A�ƊE�̉c�ƌ���ł͖w�ǎ�舵���Ȃ��B���k����̗l�ȋƎ҂�r������ׂɂ́A�ƊE�Ƃ��Ė����J�������j�[�Y�ɉ������g�݂��K�v�����A���ꂪ������Ƃւ̃��X�N�}�l�[�����ɂ��q����B�V���s��E�O���[���V�[�g�E�x���`���[�t�@���h�E�x���`���[�����ւ̎�g�݂́A�ƊE�̗��鎑�{�s��̊�Ս��Ƃ��čl���鎞����������Ȃ��B
�@
|
��Ƃ͊���̂��̂łȂ��ƒS����b�ɃR�����g�����̂��₵�����A�ԈႢ�Ȃ���Ƃ͊���̂��̂ł�����B�����āA�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�́A�X�e�C�N�z���_�[�ɔz�����ꂽ���̂ł��邪�A������ɏ�������̗�������Ƃ����������т���Ă���ƐM�������B�o�ώY�ƏȂ̊�Ɠ�����������U���Ɍ��\���ꂽ���ɂ����Ă��A�o�c�ɒ��ڊ֗^���邱�Ƃ̂Ȃ���ʊ���i�@�֓����Ƃ��܂ށj�ɂƂ��āA�o�c�҂ɋ߂��Ƃ���ŁA��Ɖ��l�̌���ɂ��ă��j�^�����O����d�g�݂Ƃ��āA�ЊO������E�ЊO�č����Ɋ��҂���ӌ��������Ƃ���Ă���B��ʂ̑�O�Ҋ�����A�l�a�n�A�����h�q��̓����Ȃǂ��A�Ɨ����̍����ЊO�̖ڂŁA��Ɖ��l�����コ���邩�ǂ����Ƃ̎��_�Ń`�F�b�N���ė~�����̂ł���B
�@�������A���؏���Ƃɂ����Ă��ЊO������́A�č���ݒu��Ђ̂T�T�D�X�����������Ă��Ȃ��B�i�����́A���؏���ЃR�[�|���[�g�E�K�o�i���X�����Q�O�O�X�ŁA�Q�O�O�W�N�̊e�ЃR�[�|���[�g�E�K�o�i���X�����x�[�X�ɏW�v�B�Ȍ�̐��������l�j�܂��A�ЊO����������Ă��A�e��ЁE�W��ЁE�劔��E�e���Ȃnjo�c�҂Ƃ̊W���߂��҂��S�P�D�W���ł́A���̓Ɨ��������ɂ��Ȃ�B�@�Ɨ����̍����ЊO����������؏��K���ŋ`���t�����邩�A���Ĉȍ~�̏�ꃋ�[�������Œ��ڂ����Ƃ���ł���B
����̋c�_�Ƃ��āA�č�����ݒu��Ёi�}�U�[�Y��18�Ђ������j�́A���̔������ЊO�č����ł��邱�Ƃ��`���t�����Ă���̂ŁA�č�����@�\�̏[������l����������悤�����A�ЊO�č����̂Q�O�D�S���͐e��ЁE�W��ЁE�劔��E�e���Ȃnjo�c�҂Ƃ̊W���߂��҂ł���Ƃ������������B
�����ƂƂ��ẮA��Ɖ��l����ׂ̈̔��f���o����@�\�ŁA������o�c�҂Ɍ����@�\�������Ɨ������厖�Ȃ̂ŁA�Ɨ�������̏�ꃋ�[����������̂Ȃ�A��Ɖ��l����̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�i�t���̗l�Ȃ��̂�����������\���A�����Ƃɓ������f�ޗ��Ƃ��Ē���d�g�݂�����Ă͂��������낤���B
���̕�������R�X�g�Ƃ��ĕ��ׂ���Ă��A�����Ƒ��̃N���[���ɂ͂Ȃ�Ȃ��B
���ɃR�[�|���[�g�E�K�o�i���X�����J�������߂���̂Ƃ��āA������ւ̃C���Z���e�B�u�E��V�W�����邪�A�X�g�b�N�I�v�V�����R�R�D�U���A�ƐјA����V���P�V�D�R���̊�Ƃ��������Ă���B�ƐјA����V���x�Ƃ��ẮA�X�g�b�N�I�v�V�����͍D�܂����v���邪�A�����ƂƂ��ẮA�ЊO�������ЊO�č����ɕt�^����K�v�����邩�A�t�^�Ώۂ͂ǂ̃}�l�[�W�����g�͈̔͂܂łȂ̂��A�����s�g�̏������ƐтƘA�����Ă��邩�A���A�����̑ސE�ԘJ�����x�Ƒ�ւƂ��ẮA�t�^�����E�s�g�������K���ȂǁA���̓X�g�b�N�I�v�V�����̒��g�ɂ��ĊJ���y�ѕ]��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��V�z�̌ʊJ���Ɋւ��ẮA�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�@�\�セ��قǖ��ł͂Ȃ����A�����\�i�ׂɔ������ӔC����K�肪�芼�ɒ�߂��Ă���ꍇ�́A�����I�ȑ���V�Ƃ��ĊJ�������ׂ����낤�B
����ɂƂ��ċN�Ƃɑ����̓I�s�����N������ł��銔�呍��֘A�̉^�c�Ɋւ��鎖�́A�����I�ɏd�v�ȕ����ł��邪�A�ŋ߂̒��ړx�͒Ⴂ�悤�ɂ��v���B
�E����ʒm�̑��������F�@���������3�c�Ɠ��ȏ�ȑO�ɔ���������Ƃ́A�S�̂̂R�R�D�O��
�E����W�����̉���F�R�����Z���̂����W���������������Ђ́B�R�W�D�S��
�E�d���I���@�ɂ��c�����s�g�F�l�b�g�ɂ��c�����̍s�g�ȂǁA�d���I���@�ɂ��c�������s�g�ł����Ђ͑S�̂ɂQ�O�D�S���Ɩ����ɒႢ�B�܂���������@�֓����ƌ����c�����s�g�v���b�g�z�[���ւ̎Q���Ґ����R�R�W�Ђɗ��܂��Ă���̂́A���̖��ɑ����Ƒ��̊�{�p�����^���B�v���b�g�z�[���Q���̃R�X�g�����ł���A��������������S���Ă͔@�����B
�Ō�Ƀf�B�X�N���[�W���[�̖��ɂȂ邪�A�l����������̒���I�J�Ê�Ƃ͑S�̂̂Q�U.�X���A�A�i���X�g�E�@�֓����ƌ���������J�Â͂V�O.�X���A�C�O�����ƌ���������J�Â͂P�U�D�R���ƂȂ��Ă���B
�ʊ�Ƃ̂h�q�ɑ���X�^���X���قȂ�͍̂\��Ȃ��Ǝv�����A����ԂⓊ���ƊԂŁA��Џ��Ɋւ�����̔�Ώ̐����������邱�Ƃ́A�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�����肪����B���̗l�Ȕz���Ƃ��āA��������e�̃z�[���y�[�W��ł̊J���́A�K�{�Ɨ������Ă��������悤������⋦��́A��Ƃɓ���������ׂ��ł���B�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̊�Ս��ׂ̈ɁB
|
�@����Ђ̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�ɂ��āA�i�N�c�_����Ă����B���Z���̋��Z�R�c��ł́g�䂪�����Z�E���{�s��̍��ۉ��Ɋւ���X�^�f�B�O���[�v�h�ɂ����ĂQ�N���A�o�ώY�ƏȂł͌�����̖��̂��ς���Ă��������A�����T�N�ȏ�͋c�_����Ă����B
�@���������A���̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X����́A���ׂ̈������̂��낤���v���o���Ă݂����B�O���@�̉����E��Ж@����ɂ��A�ψ���ݒu��ЂȂlj�Ќ`�Ԃ̑I�����͐����L�������B�܂��������̌�������������A��Ɠ����̂�������R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�Ƃ��ċc�_���ꂽ�B�������A���{�̊�Ƃ̊�Ɠ����̂�����Ƃ͕ʂɁA����͏���Ђ̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�����Ȃ̂��B
�@�P�O�N�ȏ�O�̑O����Z��@�ŁA���Z�@�ւۗ̕L���銔���̎M�Ƃ��āA�O�l���l�������Ȃ����A���ۓI�ȓ�����Ƃ��āA�C�O�ɒʗp����R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̋��������߂��Ă����͂��������B
�@���̊ԁA�����h�q��c�_��s����v�����A�l�a�n��l���`�ł̎������Ɗ���̗��v�������Ȃǂ����݉������B�Ăr�n�w�@�Ȃǂ̉e��������A�����������������ꂽ���A���{�̏���Ђ̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�́A���ۓI�ȓ��������݂ĉ��P���ꂽ�̂��낤���B
�@�P�V���A���Z�R�c��̃X�^�e�B�O���[�v�E�o�ώY�ƏȂ̊�Ɠ���������ꂼ�ꂪ�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X����ɂނ����������\�����B���Z�R�c��̕��́A���ɐٍe�i�U���P�P���j�Ŏ��グ�Ă���̂ŁA�����ł͊�Ɠ�����������̒T�v�ɂ��ďЉ�����B
���e��Z�߂�ƁA
����Ђ̊�Ɠ����̌`�Ƃ��āA�ȉ��̂R�̌`�Ԃ�����O��ŁA
�`�F�ψ���ݒu��Ёi���؏���Ƃ̂Q�D�R���j
�a�F�č�����ݒu��ЂŎ������ɎЊO�����������i���S�R�D�V���j
�b�F�č�����ݒu��ЂŎ������ɎЊO����������Ȃ��A�č�����̎ЊO�č����̂݁i���T�T���j
�J�b�R���̎���܂��āA
�y�ЊO�����i������E�č����j�̓Ɨ����z
�E���Y��Ћy�т��̎q��Ђ̂b�d�n���łȂ����ɉ����āA�e��ЁE�d�v�Ȏ����̐e�����܂߂Ăb�d�n���łȂ����Ƃ�Ɨ����̗v���ɁB�i�R�Ȃ����T�N�N�����o�߂��Ă���Ηv�������Ƃ̍l��������j
�y�ЊO������z
�E��萔�̎ЊO���͓Ɨ�������̓��������[�����B
�E����������ȏꍇ�͐��������߂�B
�y�@�K���z
�E��Ж@�����Ə��K�����̐����g�ݍ��킹��O��B
�ȏ�̂悤�ȓ��e�ƂȂ��Ă��邪�A�����̌o�ϊ�@���ӎ����āA���Č^�K�o�i���X�����ւ̐M���̗h�炬������̂��낤���A�Ɨ����̊m�ۂɊւ��Ă͏����g�[���_�E�����Ă��銴������B
�@�������A���̏���Ђ̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�����ɂ��āA�ʂɉ��Ă̔N��������������ł͂Ȃ��A�V�����̋@�֓����ƂȂǁA���ۓI�ȓ������f��ɑς��A����[�𑖂��ĊC�O�����Ƃ̐M�F�Ă����Ȃ���A�����͓����s��ɏW�܂�Ȃ��Ƃ̔F�����A�s��W�҂ɂ͂������͂����B
�@���̊�{�ɋA���āA�����[���ł̋K���������W�҂ɂ͖]�݂����B �@
|
�@����Ђ̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�Ɋւ��鋭���Ă��A�U���P�O�����Z�R�c��́g�䂪�����Z�E���{�s��̍��ۉ��Ɋւ���X�^�f�B�O���[�v�h�ŁA���ĂƂ��Ė��炩�ɂȂ����B
���̃X�^�f�B�O���[�v�ł̋c�_�́A�ߋ����x�����グ�����A���Ă��o���Ƃ���ł���A���̑S�̑����Љ�āA����̓W�J�𐄑����Ă������B
�@���Ăɂ��ƁA�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̖��́A��ƂƓ����Ƒo���̖��Ƃ��Ă��邪�A�܂����{�s��ɂ������Ƃ̖��s�����A�K�����鎖���Ƃ��āA�ȉ����������Ă���B
�P�D�V�����̔��s��
(�A)��O�Ҋ���������ʂɂ��Ă̑Ή�
�\�����g�r�̏ڍׁE�����\���Ƃ̎��{�W�E���Ə�̌_���挈�߁E������ۗ̕L��ۗL���j�̏ڍׁE���������̎蓖�Ă̊m�F�Ȃǂ̊J�����A�@��J���y�ю�������[���ŁB
�L�����s���ǂ������m�łȂ��ꍇ�A���s���z�ɂ��Ċč����̈ӌ��\���y�т��̌��\�̋`�����B
(�C)����x�z���̈ړ����悤�ȑ�K�͂ȑ�O�Ҋ����������ւ̑Ή�
�\��O�҂���̈ӌ��\���Ⴕ���͊��呍��c�ցB������ł̃`���b�N�̋����B
(�E)MSCB���̔��s�ɑ���Ή�
�\���Ƀ��[���͐�������Ă��邪�AMSCB�ɗގ�����������ΏۂցB���s�����̍�������s�g���J���B
(�G)���ǂ��������ɂ����鎷�s�ʂ̏[���E�A�g������
�\���ؖ@�P�T�V���i�s���s�ׂ̋֎~�j�ᔽ���A�ے����̑ΏۂցB
�Q�D�L���b�V���A�E�g
�\������Ή��Ƃ��čs����������̒��ߏo���Ɋւ��āA��O�Ҋ�����̗\�肪����ꍇ�́A�J�����`�����B
�R�D�O���[�v��
�\�q��Ђ̌o�c��̏d�v�ȍs�ׂ�o�c���A�d�v�ȉe����^����ꍇ�́A���Y�q��Ќo�c�w�̌����̊J���B
�S�D�q��Џ��
�\��������[���ŁA�e��Ђ���Ɨ����̍����ЊO������y�ъč����̑I�C�����߂铙�A��������̗��v�ɔz���B
�T�D�����̎�����
�\�������̊J���ցB��s�ۗL���ɂ��ẮA��s���ۗL���������@�\�̊��p���ʼn������邱�Ƃ�]�ށB
���ɁA��Ђ̋@�\�ł���K�o�i���X�@�\�Ɋւ��ẮA
�P�D�������̂����
�\��������R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̃��f����A����Ђ̓K�o�i���X�̐��̓��e�Ƃ����I���������R���J���B
�Q�D�č����̋@�\����
�\�č����č����x����l�ށE�̐��̊m�ہA�Ɨ����̍����ЊO�č����̑I�C�A�����E��v�ɒm����L����č����̑I�C�B
�R�D�ЊO������E�č����̓Ɨ���
�\�Ɨ����Ɋւ����Ђ̍l�����̊J��
�S�D�č��l�̑I�C�c�āE��V�̌��茠
�\�č��l�̑I�C�c�āE��V�̌��茠���A�č����̌����Ƃ���B
�T�D������V�̊J��
�\������V�̌�����@�y�ѕ�V�̎�ޕʓ���̊J���B
�܂��A�����Ƃɂ��c�����s�g�����߂�����ɂ��ẮA���ɋ@�֓����Ƃ̋c�����s�g�ɂ��āA
�@����ҐӔC�Ɋ�Â��K�ȋc�����s�g�̓O��
�A�c�����s�g�Ɋւ���K�C�h���C���̍쐬�y�ь��\
�B�c�����s�g���ʂ̌��\
���A�@�֓����Ƃ��ꂼ��ɋ��߂��Ă���A����Ђ͂���ɑ��āA
�@����Г��ɂ�銔�呍��c�Ă̋c�����ʂ̌��\
�A�c�����s�g�ɌW��������i������̕��U�A���W�ʒm�̑��������A�z�[���y�[�W�ւ̌f�ړ��j
�B�c�����d�q�s�g�v���b�g�z�[���̗��p���i�i����P�����x�j
�C�L���،����E�����������̊��呍���o
�ƂȂ��Ă���B
���낢��c�_���������悤�����A�����͎�ɏ��K���Ȃǂ̎�������[����A�J���ȗ߂̉����ɂ���č���i�߂�ꂻ���ł���B
|
����Ƃ̃K�o�i���X�����Ɋւ��āA���Z�R�c��́g�䂪�����Z�E���{�s��̍��ۉ��Ɋւ���X�^�f�B�O���[�v�h�ɂ����āA���c�_����Ă��邪�A�ψ���ݒu��Ђł���č�����ݒu��Ђł���A�ЊO������E�ЊO�č����̓Ɨ��������ɂȂ��Ă���B
�@������Ƃ܂Ŋ܂߂���Ж@����`����Ƃ���́A�ЊO������E�ЊO�č����̓Ɨ����́A����ЂƂ��ăK�o�i���X�Ɋ֗^����ē@�\�̒��ŁA�{���ɎЊO�̃`���b�N�@�\�������̂��B�e��Ђ�A�������ʼn�Ђ̋Ɩ��ɋ߂��҂��A�O���̖ڂŋƖ����s���ēo����̂��A�ЊO������E�ЊO�č����̓Ɨ����ɂ��āA���ɊC�O�����ƁE�@�֓����Ƃ����莋���鐺�������B
�@�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�����Ɋւ����̓I�ȗv�]�Ƃ��ẮA�u���؏���Ђ̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�Ɋւ��铊���ƌ����ӌ���W�ɑ��Ċ�ꂽ�ӌ��̊T�v�ɂ��āv�i�Q�O�O�W�N�W���j�ɂ��ƁA�ȉ��̗v�]�����Ă���B
���啝�ȋH�߉����V�����s����ѕs�����Ȋ�����ɑ����O�Ҋ����̐���
�������������Ɋւ�����J��
�����匠��D�����������̐���
�������h�q��̓�������є��������̋���
���ЊO������̓������i�ƓƗ�������
���ЊO�č����̓Ɨ�������
���c�����s�g���̐���ɘa�ƍs�g���ʂ̊J��
�@�܂��A�C�O�̗L�͋@�֓����Ƃ̒c�̂ł���G�C�V�A���E�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�E�A�\�V�G�[�V�����i�`�b�f�`�j�́A���{��ƂɍŒ�R�l�̓Ɨ�������̓��������߂Ă���B
�@�m���ɁA��N�܂ł͔����h�q����u�[���̗l�ɓ��������Ƃ������Ă������A�啝�ȑ�O�Ҋ����⊔�������Ȃǎ��{����ŁA�ꕔ�V����Ƃ̖�肠��s�����ڗ������B
�@�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X����������A�o�c�̓����������܂��������A�m���ɓ������Ղ����낤���A�ł́A���{�̊��́A�{���ɃR�[�|���[�g�E�K�o�i���X�ɖ�肪����̂Ŕ����Ȃ��̂��낤���B
�@��N�A�O�l�͂R�D�V���~���{����z�������A����͋��Z��@���_�@�Ƃ���w�b�W�t�@���h���̔��肪��̂������Ƃ������������B�������A���Z�r�b�N�o���ȍ~�����ɑ������Ă����O�l�������䗦���A�������N�œ��ł��ƂȂ��Ă��āA�C�O�@�֓����Ƃ��A���{�����i��ł���Ƃ͌����Ȃ����Ƃ������ł���B
�@�ł́A�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X����������A���c�_���Ă���悤�ȓƗ�����𐧓x�����������A�O�l��@�֓����Ƃ́A���{�����̂ł��낤���B
�@�j�b�Z�C��b���������A�Ɨ����̍����ЊO�������L�����ƂƁA����ȊO�̊�Ƃ̊O�l�����䗦���r�������|�[�g�����\���Ă���B
�K�o�i���X�́A�C�O�����Ƃ̖����I��v���ƂȂ�̂�
�����|�[�g�ɂ��ƁA
���Ɨ����̍����ЊO������̂����Ђ̊O�l�����䗦�́A���ςłP�V�D�S���ƁA�ЊO������̂��Ȃ���Ђ̕��ςP�Q�D�U����傫�������Ă���B�i�Ɨ����̒Ⴂ�ЊO������������Ȃ���Ђ̕��ς́A�P�Q�D�V���j
���ߋ��P�P�N�Ԃ̊O�l�����䗦�̑������݂Ă��A�Ɨ����̍����ЊO������̂����Ђ́A�X���������Ă��邪�A�ЊO������̂��Ȃ���Ђ́A�U�D�W�������ɗ��܂��Ă���B�i�Ɨ����̒Ⴂ�ЊO������������Ȃ���Ђ́A�T�D�W�����j
�@�Ɨ����̍����ЊO������̓������A�C�O�����Ƃ̖����I�ʂɉe�����y�ڂ����\���́A�����ƌ�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@
|
�\��̗l�Ȃ��Ƃ������ƁA��̑O�Ȃ�唼���V�K���ׂ̈̊��[�������ɌW����̂ł��������A���@�i��Ж@�j�ł̎��{����̌������R�����Бg�D�̏_��ȂǁA����Ђ���蓾�鎑�{�����l�����āA����y�ѓ����Ƃɔ��f�ɑ傫���e�����邱�Ƃ����������Ȃ����B
�@�Ⴆ�A
���ɒ[�Ȋ��������⊔������
�������s��ƍْ�̂��Ղ��l�r�b�a�E�D�抔���̔��s
����Ɖ��l��ʑ�����\���̂��锃���h�q��
����ʂŎx�z���傪�ς��悤�ȑ�O�Ҋ���
���J������������̐����̋��U�L��
�@�����̎��ɑ��āA���܂ł͌ʂɑΏ�������A��ƍs���K�͂Ƃ������ƂŁA����Ƃ����炷�ׂ������Ƃ��Ē�߁A���\�[�u�Ɍ����y�i���e�B�������Ă����B�i�K���J�����̋K���ᔽ�Ɋւ��ẮA���P�������߁A���p�~�܂Ŏ��鎖�Ă��ǂ����͌ʂɐR�����Ă����B�j
�@�ɘ_���Đ\����Ȃ����A���Ƃ���������ł́A���̊�͖��m���������A���ێ��ׂ̈̃��[���A�Ⴕ���͏��p�~�Ɏ��郋�[���ᔽ�̊���A���{�s��̕ω��ɒǂ����Ă��Ȃ������B
�@���̎��Ɋւ��āA�T���P�X�������A���܂ł̊�ƍs���K�͂���ꃋ�[��������悤�Ȑ��x�������D�]����Ă���B
�@�܂�A���܂ł̊�ƍs���K�͂̏��炷�ׂ������Ɉᔽ�����ꍇ�A���܂ł̌��\�[�u�ɉ����āA���_������Ƃ������K�I�y�i���e�B�[���ۂ����Ƃ����[��������B�����āA���P���̒�o�����߁A�����Ԃ͓��ݒ��ӎs������Ƃ��Ďw�肷��B
�@�܂��A�K���J�����̋K���ᔽ�ɂ��Ă��A���܂ł̉��P�������߂邱�Ƃɉ����A���\�[�u�𖾕������A���_��������ۂ��B������A�����Ԃ͓��ݒ��ӎs������Ƃ��Ďw�肷��B
�i���܂ł́A���ӊ������x�͔p�~����B�j
�@��g�͈ȏ�̗l�ɁA�i���ێ��ׂ̈́j���[�����m�ɂ�����̂ŁA�ʂɐ�������邱�Ƃł͈ȉ��̑Ή�������B
�q��O�Ҋ����ŁA��ʂ̊��������s�����ꍇ�r
�E�������R�O�O������ꍇ�́A���p�~�B
�E�x�z���傪�ٓ������ꍇ�A�x�z����Ƃ̎���ɂ��ĔN���ȏ�`���B�R�N�ȓ��Ɍ��S�����������ʑ����A���̊���̗��v�N�Q���邨���ꂪ�傫���ƔF�߂���ꍇ�A���p�~�B
�E�������Q�T���ȏ�̏ꍇ�́A�Ɨ����̋����O���̈ӌ����Ⴕ���͊��呍��ł̌��c�i�ً}���̍����ꍇ�͏����j
�q��O�Ҋ����r
�E������̎����蓖�Ă̊m�F
�E���s���z�̎Z�荪���y�ы�̓I����
�E�����悪���Љ�I���͂ƊW�Ȃ��|�̊m�F���@���@��K�v�Ƃ���B
�q���������r
�E���傪�s���ɋc�����������悤�ȏꍇ�́A���p�~�B
�q�l�a�n�r
�E�l�a�n���s���ꍇ�A�K�v�\���ȓK���J�����s�����Ƃ��A��ƍs���K�͂̏��炷�ׂ������Ƃ��Ē�߂�B
�@�ȏ�̂悤�ȁA���K���̖��m���́A���{�s��ł͍D�܂������Ƃł��邪�A����̊�ƍs���K�͐����ɂ������āA���ւ̎��O���k�v�����A����������Ă���B
�@���x�Z���ׂ̈ɂ͕K�v�Ȃ��Ƃ�������Ȃ����A���O���k���A�s���߂��������K���ɂȂ�ʂ悤�A��ƂƂ̑Ή�����ŁA�K�������̖ړI�̓O����A���ɂ��A���肢�������B
|
����Ђ̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�����ɂ��āA���K���ɂ��A��߂悤�Ƃ������Z�R�c��̓����́A���`�����Ă��邪�A�挎23���A���̏�ꐧ�x�������k����A����Ђ̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�����̈�Ƃ��āA�u�����҂����S���ē����ł�����̐����v�Ɓu����Ə���Ђ̑Θb���i�̂��߂̊������v��ړI�ɁA�ȉ��̒����\����Ă���B
���S���ē����ł���s������̐����Ɍ�����
�̃|�C���g�́A
����O�Ҋ����ɂ���
�@�E�����s�����̂R�O�O��������̂́A������̏��Ɋւ���R���̑Ώ�
�@�E�����s�̂Q�T������R�O�O���́A���呍��Ⴕ���͓Ɨ��@�ւ���̈ӌ��m�F
�@�E�����悪�x�z���̈ړ��̂���ꍇ�A���̊���Ƃ̊Ԃ̎���ɂ��Ċm�F
�@�E�P�O�����f�B�X�J�E���g�̏ꍇ�A�č����̈ӌ������\�iCB�A�V���\�͕K�{�j
�@�E������̎����蓖�Ă̊m�F�A���\
�����������ɂ���
�@�E���啹���̌��ʁA�����̊��傪�A�x�z���̂Ȃ��P����������ֈڍs��]�V�Ȃ���������悤�ȃP�[�X�́A������ɂ������R���̃v���Z�X��݂���B
�@�E����̗��v�ɂł������z�����āA�����銔��̊��唃�搿�������m�ۂ����悤�ȑ�֎�i������ꍇ�ɂ́A��������߂�B
���c�����s�g��e�Ղɂ��邽�߂̊������ɂ���
�@�E�W�����J�Ó��̉���i�ŏI���̈���O��9���ȏオ�W�������́A�Q�O�O�W�N�x�S�W���Ɖ��P����Ă��邪�A�ŏI�T�ւ̏W���́A�܂��W�T���j
�@�E���W�ʒm�̑��������i�������瑍��܂ŁA�@������̂Q�T�Ԃɑ��A����18���ƂȂ��Ă���j
�@�E���W�ʒm���̓d���I�iHP�ł̊J���́A�S�̂̂R�T���̂݁j
�@�E���W�ʒm���̉p��i�S�̂̂P�T�����Ή��j
�@�E�d�q���[�̓����i�S�̂̂Q�P�D�X���������j
���c�����s�g�̊J���ɂ���
�@�E���B�ł́A�C���^�[�l�b�g�ɂ��J�����`���t�ւ̕����������肵�Ă���B
�@��Ж@����܂łɁA�����@�ł͕ێ�I�ɉ�����Ă�����Ђ̎��{����ɂ��āA���Ɋ����ցE�V���\���x�E��ފ��̐����E���������ƕ����E���{�������̈������A������߂��āA��������蓾�鎑�{����̎��R�x�́A����10�N�Ő����Ƒ������B
�@�ܘ_�A��������Ɉ��e����^����悤�Ȏ��{����́A�����ꕔ�̊�Ƃɉ߂��Ȃ��̂����A����Ђł���ȏ�A�s���葽���̊���y�ѓ����ƂɑΉ�����`���́A�S�Ă̏���Ђ��������̂ł���B
�@�ŋ߂̊J�����x�̉��v��A���������Ή��ŁA��Ƃ̕��S�͑����������Ă���Ǝv�����A�悸�͔�r�I�R�X�g��������Ȃ��AHP�ł̏��J���̋����E�d�q���[�̓����Ȃǂ́A���X�ɑΉ����Ăق����B
�@�܂��A�@�֓����ƁE�C�O�����Ƃ̋c�����s�g�𑣐i����c�����s�g�v���b�g�z�[���̎Q�����A�܂��R�R�X�ЂƓ��؏���Ђ̂P�T�������Ȃ̂́A���ł���B���̐��x�Ȃǂ́A�{���͊�Ƒ��̃����b�g���傫���͂������A�R�X�g���S��������Ƒ��̈ӌ�������A������������̃C���t���Ƃ��āA��������炪�R�X�g�S���A��Ƃ̗��p�����������Ă͔@�����낤���B
|
3�������Z���\���A�����Ȃ�ɂȂ��Ă������A��Ƃɂ���Ă�6���̊��呍��ւ̏����ɒǂ��鎞���ł�����B��Ж@�Ƃ�����Ɗ������x����@�����A�Q�O�O�U�N5��1���Ɏ{�s����Ă���A���傤��3�N���o���A���̊ԁA��Ƃ̕s�ˎ������������A���{�s��ł��A��ʑ�O�Ҋ�����MSCB�A�����h�q�����Ȃǂ��������B
�ʂɁA�C�O�����Ƃ��ӎ����Ȃ��Ƃ��A���J��Ƃ̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�����́A���{�s��ɂ�����ŗD��ۑ�ł���B
�@�K�o�i���X���ē@�\�ł��邩��A��Ƃ̓���̍s�����ē���̂́A�������̋@�\�̊�b�B�Ƌ��ȏ��I�ł��邪�A�O�i�̖��ɑΉ�����ׁA�������ɁA�O���̓Ɨ����̋����@�\���A������悤�Ƃ����̂��A���Z�R�c��ł́A�c�_�̒��S�ɂȂ��Ă���B
�@��Ƃ̃K�i�i���X���ē@�\�̌`�́A�ȉ��̂R����B
�P�D�ψ���ݒu��ЁF�i�w���E��V�E�č�3�̈ψ����Ȃ�A�e�ψ���̔����͎ЊO������j
�@�@���؏��̂Q�R�T�P�В��A�T�U�ЂŁA�S�̂̂Q�D�R��
�Q�D�ЊO������F�i���݂̋c�_�́A���̎ЊO������̓Ɨ��������߂��h�Ɨ�������h���x�������A����Ђɋ`���t����Ă����S���j
�@�@���؏��̂Q�R�T�P�В��A�č�����ݒu��ЂQ�Q�X�T�Ђł��邪�A���̒��ŁA���݂̊�̎ЊO������������Ɛ��́A�P�O�O�R�ЂŁA�S�̂̂S�R�D�V��
�R�D�ЊO�č����F�č�����̔������A�ЊO�č����łȂ���Ȃ�Ȃ��B
�@�@���؏��̂Q�R�T�P�В��A�ЊO������̂��Ȃ��������ł̊č�����ݒu��Ђ��A�P�Q�X�Q�ЂőS�̂̂T�T��
�@���肪�\�z����铌�؏��K���ŁA�Ɨ�������̓������`���t�����邩������Ȃ����A�R�D�̗l�ȉ�Ђ��ߔ������߂�̂�����A�悸�͊č����̋@�\���������Ă͂ǂ����Ƃ������������悤���B
�@�ȉ��A���Z�R�c�������A���̈Ă̓��e������ƁA
���ЊO�č����i�ЊO��������j�̎ЊO�����A�Ɨ����̊ϓ_���猵�i������@����
���č�����c���́A�ЊO�č����B�ЊO�č����̖�������
�������h�q��ɑ��ẮA�ЊO�č����i�ЊO������j���\�����Ƃ�����ʈψ���Ŕ��f
����K�͑�O�Ҋ��������E�e�q���ɂ��āA�č�����ɂ��ӌ����J��
�������Ăɂ��ẮA���̐���ɂ��Ċč��������f����悤�@����
���č��l�̑I�C�E�č���V�Ɋւ��āA���݂̓��ӌ�����A��Č���V���ɕt�^
���č��l�ɂ����������č����̊��呍���o�A�����Ċ��呍���o�̎��ƕy�ъč�����č��ɓ��������̉^�p���ʓ��Ɋւ���]�����L�ڂ���悤�@����
�@��Ж@�ɂ���āA��Ƃ͑��l�ȉ^�p�`�Ԃʼn^�c����邱�Ƃ��\�ƂȂ������A���J��ЂƂ��Ă̐ӔC�́A���̉^�c�̓����������߂遁�܂�Ɩ����ǂ̗l�ɊǗ�����A�܂��N���ǂ̕����Ɋւ��āA�ӔC������̂��A���m�ɂ��邱�Ƃ��Ǝv���B
|
����Г��̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�́A���̋�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����B
�@�@���x�c�_�͕ʂɂ��Ă��A���{�s��I����������A���S���ē������Ă��炤��Ƃ݂̍�������ڂ���Ă���̂��낤�B�@
�@���݁A�o�ώY�ƏȂ̎�Â���u��Ɖ��l������v����Z���̋��Z���x���v�ׂ̈́u�䂪�����Z�E���{�s��̍��ۉ��Ɋւ���X�^�f�B�O���[�v�v�i���Z�R�c��j�ŋc�_������A�K�o�i���X�����ւ̎��g�݂̎�v�e�[�}�ɂȂ��Ă�����̂Ƃ��ēƗ�������̓���������B
�@���̓Ɨ�������Ɋւ��ẮA�C�O�̋@�֓����ƂȂǂ��������߂Ă�����̂ł͂��邪�A�ł͉�Ж@�ɒ�߂�ЊO������ł͕s���Ȃ̂��B��Ж@�{�s���ɂ��A���̎ЊO������̓Ɨ����͖��ɂȂ������A��Ж@�͏���Ђ����̂��̂ł͂Ȃ��̂ŁA�ЊO���Ɨ����̖��́A���ǂ��ꂼ��̗���Ŕ��f����Ƃ������ƂɂȂ����B
�@�������A���q��Ђł̎ЊO��������e��Ђ��v����悩��ł́A���������̎ЊO�̈Ӗ��͉��ł��낤���ƁA�����ƂłȂ��Ƃ��v���B
�@�܂��A���{�̎�v�ȋ@�֓����ł�������N������A����i����ƔN���A����j�ł́A����16�N�Ɂh����c�����s�g��ɂ�����ЊO������̓Ɨ����Ɋւ��锻�f��h�Ƃ��Ĉȉ��̓Ɨ����̂Ȃ��v�����グ�Ă���B
�@��Ɩ��͂��̎q��Ђ̋Ɩ����s����͎Ј��Ƃ��ċΖ��o����L����ҁB�i5�N�ȏ�o�߂����ꍇ�͏����j
�A��Ƃ̑劔�喔�͎�v�Ȏ�����Ƃ̋Ɩ����s����͎Ј��B
���劔��Ƃ́A���c�����̂R���̂P�ȏ�̊�����ۗL����҂������B
����v�����Ƃ́A���Y��Ƃւ̔���グ����ʂP�O�Ђɓ���悤�ȉ�Ђ������B
�B��Ƃ��������V�ȊO�i�R���T�������j�ɕ�V���Ă���B
�C��Ƃ̎�����Ɛe���W�ɂ���B
�D���Y��ƂƂ̊ԂŎ�����𑊌݂ɔh�����Ă���B
�E���̑��A���Y��ƂƂ̊Ԃɗ��Q�W��L���A�ЊO������Ƃ��Ă̐E���𐋍s����̂ɂӂ��킵���Ȃ��ƔF�߂���ꍇ�B
�@�ł́A�Ɨ�������ŏ���Ƃ̌o�c�҂ɂƂ��āA���S��X�N�ȏ�̃����b�g�͂���̂��B
�C�O�@�֓����Ƃ������悤�ɁA�Ɨ��������3�l�܂ő��₵����A��Ƃ��x�����铊���Ƃ͑�����̂��B���_�́A���x������̎��،������Ȃ��ƌ�����Ȃ����A�ȉ��̃R�����œƗ����̍����ЊO�������I�C���Ă����ƂƁA�����łȂ���Ƃ̊O�l�������䗦���r����Ă���B
RIETI�R����
�Ɨ�������̓����́A�C�O�����Ƃ̎s��Q���𑣂��̂�
���ʂ�3���ȏ�ۗL�䗦���Ⴄ�������B
�@�Ɨ���������@�֓����Ƃ̓����𑣐i����v�����ǂ����͐��m�ɂ͕�����Ȃ����AM&A���ƍĕ҂Ȃǂ̏d�v�Ȍ��������ꍇ�A���i�͂ɑ��鐧��V�X�e���́A����Ђ̒��ɂ����������ǂ��B�������A��Ж@������@�A�Ⴕ���͌��J��Ж@�Ƃ����@���Œ�߂�̂ł͂Ȃ��A��������[���̂悤�ȃ\�t�g���[�ł̕����A���{�s��W�҂Ƃ��Ă͍D�܂����v���B |
�R���Q�U���̕ŁA�č��̎Ѝs��i�Ƃ����Ă����i�t����Ƃ́j���`�����Ă������A���{�̔��s�s��́A�Ƃ����ɂ͒��������Ǝv���B
�@���������A�M���ł��鎑�{�s��łȂ���A���X�N�}�l�[�������t���邱�ƂȂǏo����͂����Ȃ��B���ׂ̈́A���Z�E���{�s����v�ł����ė~�������A�ĎO���`�����Ă���悤�ɁA�����Z�R�c��̉䂪���̋��Z�E���{�s��̍��ۉ��Ɋւ���X�^�f�B�O���[�v�ŁA����Г��̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̂�����ɂ��āA��������Ă���B
�@���[���������̎�@�_�_�͈ȉ��̂R�ŁA
�@�i�P�j�@���x�̂����
�@�i�Q�j��������[���̂����
�@�i�R�j���̑���@�̂����
�ŁA���̒��Ŋč�����@�\�̏[����Ɨ��ЊO������̊g�[�A���J��Ж@�̌����Ȃǂ��c�_����Ă���B
�@���̏���Ђ̃R�[�|���[�g�K�o�i���X�����ƖړI�ɂ́A���R���̌����ƂȂ����Ƃ̕s�ˎ�����������ł��邪�A�R�c����Ƃ��čŋ�3�N�ԂłP�P�Ђ̕s�ˎ����͂�����Ă���̂ŁA�����ɏЉ��B
�@������Ѓv���e�B�r�e�B �W���p���쐬
�s�ˎ�����̕��̓��|�[�g 2009 �N3 ����
���ɂ́A���{�s��̒���҂�����Z�@�ւ̎���������āA���{�s��ւ̐M���́A��������O�ꂷ�ׂ��Ƃ��v���镔�������邪�A�s�ˎ��Ɏ�������Ȍ������ȉ��̗l�ɏグ�Ă���B
�@���o�c�҂̖��i���X�N�F�����@�E�ېg�ɂ��B���j��3��
�@���������i���㎊���`�E�@�ߏ���̎Г��̐��j��2��
�@���@�ߏ���Ȃǂ̃��X�N�̕]���E�Ή���2��
�@���Ǘ��̐���}�j���A���s���Ȃǂ̓���������2��
�@���Ď������̖�聁2��
�ƂȂ��Ă���B
�@��Ђ͒N�̂��̂��Ƃ������c�_����䂪���̃R�[�|���[�g�K�o���i���X�c�_�͎n�܂����悤�ɂ��v�����A���ǂ���Ђ͊���̂��̂����Ǝv���Ă���l�́A���̍��̎��{�s��ɂ͂��Ȃ��B�������A����Ⓤ���Ƃ̐M���Ȃ���A���̎��{�s��̋@�\���g���Ă�����J��ЂƂ��Ă̈ێ�������̂������ł�����B
�@���ǁA�R�[�|���[�g�K�o�i���X�́A��ЂɂƂ��āA���{�s�ꂩ��M���邽�߂̎d�g�݂Ƃ������������A���J��Ђɂ��Ă���������Ηǂ��̂ł͂Ȃ����낤���B
�@��Ж@�����ł́A����Ђ̃R�[�|���[�g�K�o�i���X�͏[������Ȃ��Ǝv�����A�ꕔ�ɋc�_�̂�����J��Ж@�́A���㉮���d�˂�悤�Ȉ�a��������ł͂���B
�@�ƊE�W�҂Ƃ��ẮA��������[���̏[���ƁA���̉^�p�ɑ��āA���{�s��W�҂�����ӔC�������Ă����邱�Ƃ̂��A���̍��̎��{�s��̐M������邱�ƂɂȂ�ƐM�������̂����B
�@ |
�\�j�[�A�����A�����ē��łƁA���d�@���J�[�̃g�b�v��オ�������œ`�����Ă���B
���̔w�i�̐����Ƃ��āA�������o�ϊ��Ƌ��ɁA�����̉�Ђ��A�ψ���ݒu��Ђł����āA���̎w���ψ���̋@�\�Ƃ��āA��N���Ɏ�����̍đI���������`�F�b�N����d�g�݂��A���Ă������B
�@�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̋@�\�������Ă��鎖��Ƃ��āA�Љ���������̂��낤���A���̈ψ���ݒu��Ђ͂��Ƃ��Ƒ��Ƃ̎d�g�݂ł����āA���؏���Ƃł��������Q�D�R�������������Ă��炸�A�c��͊č�����ݒu��Ђł���B
�@����Ђ́A���̂ǂ��炩�̐��x���g���Ă��邪�A�ڂ����@���_���ʂɂ��āA�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X����̎d�g�݂Ƃ��ẮA�ψ���ݒu��Ђł͈ψ��E�č�����ݒu��Ђł͊č����̔����ȏオ�h�ЊO�h�ł���K�v������B
�@���݁A���Z�R�c��̉䂪�����Z�E���{�s��̍��ۉ��Ɋւ���X�^�f�B�O���[�v�ɂ����āA����Г��̃R�[�|���[�g�E�K�o�i���X�̂�����ɂ��āA�c�_���i�߂��Ă��邪�A���ɂ��́h�ЊO�h�Ƃ����O���̋q�ϐ��̋@�\���d������Ă���悤�Ɏv���B
�@�ЊO�Ƃ����Ă��A�@
�@�@�E�e��Ђ��v�����̊W�҂łȂ�����
�@�@�E�o�c���s�����s���Ƃ̌l�I�W���d������Ȃ�����
�@�@�E���̏�ŁA�Ɩ����s�Ɋւ���`�F�b�N�@�\����������
���A���߂��Ă���B
�ܘ_�A�ЊO������ƎЊO�č����̋@�\�͈قȂ邪�A���̎ЊO���̃`�F�b�N�@�\�������A�s����v��s����������R�ɖh����A�s�n�a��l�a�n�ɑ��Ă��@�\����h�ЊO�h�����A�����Ƃ͊��҂��Ă���B
���Z�R�c��ł̋c�_�Ƃ��ẮA
�@�@���ψ���ݒu��Ђ͖]�܂�����������Ȃ����A���{�̎���ɍ���Ȃ�����������̂ŁA�č�����̋@�\�[���ƂƂ��ɁA�Ɨ����̂���ЊO������̋@�\�Ɋ��҂��Ă͂ǂ���
�@�@���ЊO������Ɋ��҂��邱�Ƃ́A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�����ɂ�����j�o�c�҂̐����ӔC�̊m��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�L���ɂ�����j�\���̖h�~�E���S��
�Ƃ��āA�Ɨ������ЊO����𐧓x�������A����Ƃɓ���������悤�ł���B
�@�܂��A��Ђ͒N�̂��̂��Ƃ������c�_�ƂƂ��ɁA�R�[�|���[�g�E�K�o�i���X���N�̐ӔC���Ƃ��������Ƃ́A�����ł��邩��A�����ƁE���呤�����̋@�\�͉ʂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@���̕����̑Ή��Ɋւ��ẮA�����̌l�����Ƃ���������Ă���@�֓����Ƃ̃K�o�i���X�֗^���A�����Ɋ��҂���Ă���B
�@���̂��Ƃ��A�s��W�҂��^���Ɏ~�߂邱�Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă���B
���Z�R�c���
�@����Ђ̃K�o�i���X�@�\�̘g�g��
�@�_�_�����@�@�@ |
�@����i�R/�S�j�̌o�σj���[�X�ŁA��N�P�O�O�O���h���ȏ�̍��z��V���������E�����`�̊������A�ʐ^�E��������ŕ��Ă����B���z�̑������o���A�o���J���ɋz������A���̃o���J���Ɍ��I�����Ƃ����ŋ��𓊓����Ă���̂ɁA�܂��č����̓{����Ƃ����_���ł������B
�@�m���ɁA�ǂ̗l�ȋƊE�ł����Ă��A��V�͎��v�ɍv���������Ƃ̑Ή��ł���͂�������A���z�̐Ԏ��ɑΉ��Ƃ��Ă͐����s�\�ł��邵�A�{�[�i�X�Ȃǂ̎x�������A���������O�ʏ�����ꂩ�����߂Ă��܂��āA�s���������@���Ȃ��B���ꂾ���R�[�|���[�g�K�o���X�ɂ��邳�����́A���ɂ��邳���ƑԂɂ����āA�����B�̉�Ђ̃K�o�i���X�͂ǂ����Ă��܂����̂��A���Ɏc�O�Ȃ��Ƃł���B
�@�����O�̐����ɂȂ邪�A�M�҂����{�ɂ����铊����s�̕�V�ׂ����Ƃ��������B�R�N�O�̑�G�c�Ȑ����ŋ��k�����A���{�ɂ����铊����s�̏]�ƈ���l������i�鏑�₻�̑��T�|�[�g����l�������܂߂��j�̕�V�z�́A���n����1,500�`1,700���A���đ��ł�4,000�`5,000���ł������B
�@�ܘ_�A�S�̂̕�V�̍���������̂����A���̉��ē�����s�͓����悤�ȋƖ���3�{�̕�V���x�����̂��낤���B�҂��ł�����z���Ⴄ�A�����Ă���\�͂��قȂ�A�|�|�|�m���ɂ��������m��Ȃ����A��͂�ٗp�̌n���قȂ邩�炾�낤�B
�@�O���n������s�̌ٗp�́A������N�_����A�҂��Ȃ���Η��N�̌ٗp�͊m�ۂł��Ȃ��B�]���āA�҂���Ƃ��ɂ͉҂����Ƃ��ĕK�v�ȏ�̃��o���b�W�������āA���ɂ͒e���Ă��܂����Ƃ����̂�����̕č��^������s���f���̕���̈���ł͂Ȃ����낤���B
�@������s�Ƃ����r�W�l�X���f�������������̂ł͂Ȃ��A������s�̌ٗp�V�X�e�����c��ł����B
�Ƃ����āA�g���[�_�[�ɂ���A�o���J�[�ɂ���A�t�@���h�E�}�l�[�W���[�ɂ���A�Ɨ��������f���o����v���͕K�v�ł���B�������A�{���̃v���͈ꈬ��ŁA���͓�����s�g�D�S�̂����̈ꈬ��̃v���̕�V�̌n��^���Ă��܂������Ƃɂ���̂��낤�B
�@�����ٗp��O��ɂ��Ȃ���A��ƂƂ͒����t�������Ȃ��Ǝv���̂́A�������{�����ł͂Ȃ��A�O���[�o���ȏ펯�ł�����B
�@����������s���Đ����Ă����Ȃ�A�ٗp�ƕ�V���x�ɂ��āA��ƂⓊ���Ƃ̐M���ɑς�����̂ɕς���K�v������ƁA�����Ďv�����Z�s���̂��̍��ł���B
��a�����R����
���ċ��Z�ƊE�̍���V�́g�X�[�p�[�o�u���h�������̂��H |
|
|
|
�@���Z�E���{�s��ł́A��Ђ𓊎��E�Z���ΏۂƂ��Ă݂�̂ŁA�Ɩ����e������f�[�^�ȊO�ɁA��Ђ��ǂ̗l�ɉ^�c����Ă��邪�m��K�v������A�R�[�|���[�g�K�o���X�Ƃ����`�ł̃f�B�X�N���[�W���[����Ђɋ��߂�B
�@�䂪���̋��Z�E���{�s��̋@�\�����ׂ̈ɁA����Г��̃R�[�|���[�g�K�o�i���X�ɂ��āA���Z�R�c��̃X�^�f�B�O���[�v�ŁA���܂��ɋc�_����Ă���Ƃ���ł͂��邪�A�ŋ߂��̃R�[�|���[�g�K�o�i���X�̃R�A�ɂȂ�h��Ђ͒N�̂��̂��h���l���������鎖���A�R�������B
�@�P�D�{���̓��o��ʂ́A���o���厑�i�i�ׂ̓����n�ٔ����̋L��
�@�Q�D�^�Ӗ��b�́h��Ђ͊���̂ł���Ƃ����l���́A���ɂ͂Ȃ��܂Ȃ��h�����i�Q�S���̍���فj
�@�R�D���i�z�e���̋��]�ƈ��ɂ��^�c�ƁA���̗��ނ�����
�܂��R�D�ɂ��ẮA�O���t�@���h�ɔ���ꐮ�������z�e�����A���]�ƈ��B�����C�Ɏ��p������A�܂������I�ɑދ���������p���A�ٗp���������钆�Ő��Ԃ̓����U�����i�H�j�B
�܂��Q�D�ɂ��ẮA���Y�}�c���̑��Ƃ��ٗp�����̃��X�g����i�߂Ă���̂ɁA����ւ̔z��������������X�������܂������ƂɊւ��鎿��ɉ��������̂ł������B
�@���X�ɁA��Ђ͊���̂��̂����ł���Ǝv���l�Ȃlj䂪���̋��Z�E���{�s��ɂ͂��Ȃ����A������ЂƂ����d�g�݂ł́A��Ђ͓����l�̂��̂����ł��Ȃ����A�܂��Čo�c�҂̂��̂ł��Ȃ��B
�@���X�̂��̂Ƃ��������������K�łȂ��̂�������Ȃ����A��Ђ͂���ɊW����X�e�[�N�z���_�[�̂��̂Ƃ����l�������蒅���Ă���B���̃X�e�[�N�z���_�[�̒��ɁA���傪���āA��Ђ̍����I�Ȏ��Y�Ƃ����ʂɂ����ẮA����͊ԈႢ�Ȃ��]�ƈ���o�c�҂̂��̂ł͂Ȃ��A����̂��̂Ȃ̂ł���B������z�e���̌������A�苒���Ă���]�ƈ�������Ԃ��̂͐���ȍs�ׂȂ̂��B
�@�����ĂP�D�̓��o�L���ɂ��āA������Ђł�����o�ɂ͓��R���傪���āA�Ј�����̏ꍇ�̔����͎Г����[���ŊO���҂ɏ��n�ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă����B���̃��[���̉^�p���߂����āA�O���Ɋ��������n���Ă��܂������Ј��Ƒ���ꂽ���̂ł������B
�@��Ж@�̊���̏��L���̍s�g�ƁA�Г����[���̐������i�����ȕ�ړI�Ƃ��邽�߁j���A���ꂼ��咣���ꂽ���A�����n�ٔ����́A�Г����[���^�p�̐�������F�߂����̂ƂȂ����B
�@��X���Z�E���{�s��W�҂ɂƂ��āA���o�̕ɂ͖��������Ԃ��ڂ��Ă��āA���̖ړI�ł�������ȕ������̂́A������Ȃ��Ƃł���B����Ӗ��ŁA���o�̃X�e�[�N�z���_�[�ł���A���o�́h��X�̂��́h�ł�����B
�@�������A���̋L���͈�ʂŎ��グ��ׂ��L���Ȃ̂��낤���A�܂��Č��Ј��̏��n��̌l���ƍL��R�����g����ʂōڂ���K�v���������̂��낤���B��������Z�E���{�s��Ɋւ���d�v�ȋL��������Ƃ����z���́A�����̓ǎ҂ɂ�����Ǝv���A�ꌾ��\���グ��B
�@�����ȕ��Ȃ����ׂɁA���o�̃R�[�|���[�g�K�o�i���X���Ċ��҂��������A������l����������{���̈�ʋL���ł������B |
�@�����犔��̂��̂ƒP���ȓ����͖����Ȃ����Ǝv�����A���i�z�e���̈�A�̕ɂ���a�������B��Ђ��A�W�ҁ��F�̂��̂Ȃ�A���̉�Ђ̈ێ��ɂ��A�W�ґ��X���ӔC�Ƒ�����ʂ����`�������ׂ��B
�@����{����������܂߂ē����Ƃ́A�ȉ��̌`�Ō��J��Ђ̃R�[�|���[�g�K�o�i���X�ɎQ�����邪�A
�@�P�D���p�A�Ⴕ���͔��t����B
�@�Q�D�c�����̍s�g��ʂ��āA�K�o�i���X�̔�����}��B
�@�R�D�h�q�������̌o�c�҂Ƃ̉�b�̒��ŁA�o�c�ɂ��ċc�_���s���B
�������\�Ƃ���ɂ́A�����Ƒ��̔����E�c�����s�g�̊���A���J��Ƃ̌o�c�҂ɂƂ��Ė��m�łȂ���Ȃ�Ȃ��͂��B���ɋ@�֓����Ƃ́A�l�����Ƃ���̎���ҐӔC������̂�����A���̋c�����s�g�ɂ́A�^�p�ړI�ɉ��������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�J�����x�ɂ���Ƃւ̉e���͏��F���E������̂�����A����Ƃ��ĎQ�����Ă���̂ł���A�c�����s�g��ʂ��āA�K�o�i���X�ɐϋɓI�ɎQ������@�֓����Ƃ���Ă邱�������A���̍��̊�Ƃ̉��l�����߁A���ʂƂ��ċ��Z�E���{�s��̋����͂����コ����Ƃ��ɂ��Ȃ�Ɗ��҂������B
�@�������A�c�����s�g�̃C���t��������h�q���i�Ɋւ��ẮA������₻�̒���Ǝ҂�����Z�@�ւ̓w�͕s�����A���Ȃ��ۂ߂Ȃ��̂�����ł���B
�Ⴆ�A�d�q�c�����s�g�𑣐i����d�g�݂��A��Ƃ����p������̂ł͂Ȃ��A�ƊE�Ŋ�Ƌy�ы@�֓����Ƃɒ���d�g�݂����Ă͔@�����B
���Z�R�c��
�䂪�����Z�E���{�s��̍��ۉ��Ɋւ���X�^�f�B�O���[�v
�W�����i�R�[�|���[�g�K�o�i���X�j |
|
|
|
Copyright�i�b�j2009 �einancial �larkets�@�q���c�@�j�h�y�t�m�`,all rights reserved |
|
|
 ���{�s�ꌤ����������
���{�s�ꌤ���������� ���{�s�ꌤ����������
���{�s�ꌤ����������